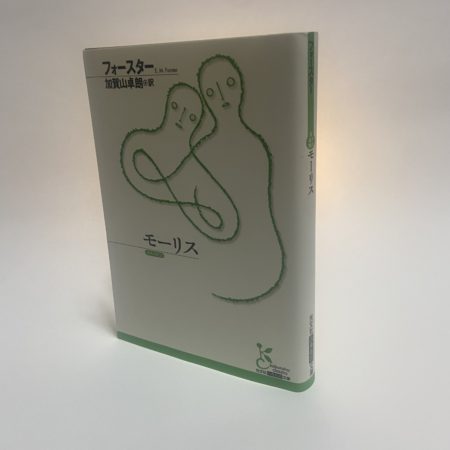夏の終わりに

今さらですが、夏に購入した夏に読むべき本を読みあさっています。夏の日差しを浴びた言葉は心を清潔にしてくれるし、眩しく輝かせてくれるものだなと”夏の本”を読んでいて思いました。
「また会おうな」「うん、きっと」
『夏の庭』湯本香樹実(著)
「死」とは何か。
好奇心旺盛な小学6年生の仲良し3人組、山下くん、河辺くんとぼく。3人は山下くんの祖母の死をきっかけに「死ぬこととはどのようなことなのだろうか」と考え始める。身近に起こることのなかった「死」。だが遠い将来に自分たちにも起こるであろう「死」。そんな死に対する目に見えない恐怖にとりつかれ始める。
そして「死ぬ瞬間」に何が起こるのだろうか。
そんな疑問を解決すべく、近所で死にそうだと評判のおじいさんを、毎日学校帰りに覗きに行くことを決意する。3人は刑事さながらに一人暮らしのおじいさん宅の庭へ密かに侵入し、窓からそっと覗いておじいさんの様子をうかがう。“子ども探偵物語”の始まりだ。彼らのミッションはおじいさんの「死ぬ瞬間」を目撃すること。
実際、死にそうなおじいさんは死んでいるかのように生活している。おじいさんは微動だにせず茶の間にひっそりと佇む。覗きのスリリングは一切期待できない。しかし、何としても「死ぬ瞬間」を目撃したいのだ。なんの面白みもない張り込みだったが、3人は根気よく執念で続ける。
だが、おじいさんはなかなか死なない。
そんなおじいさんの日常をよく観察していると、たいがい食事はコンビニで済ませているようだ。ごみは庭に捨てっぱなしで放置されており、張り込み現場は常に異臭を放つ。そんな生活臭の漂う、やさぐれた生活を送る一人暮らしの高齢者の湿っぽさが漂う光景から、少しづつ変化が訪れる。
有り余るくらいの未来の時間を持つ少年達と、残り少ない時間を過ごす老人が出会い、人生が重なった瞬間から物語は大きく動き始める。おじさんと3人の夏物語が始まる。
夏の夜空に輝く花火のシーンが美しい。鎮魂の意味を持つとされる花火。死者の魂を慰め、生者の魂を体に鎮めるとされる。おじいさんとの花火は小学校最後の何物にも代えがたい良き思い出となっただろう。