書評『心は燃える』KURI
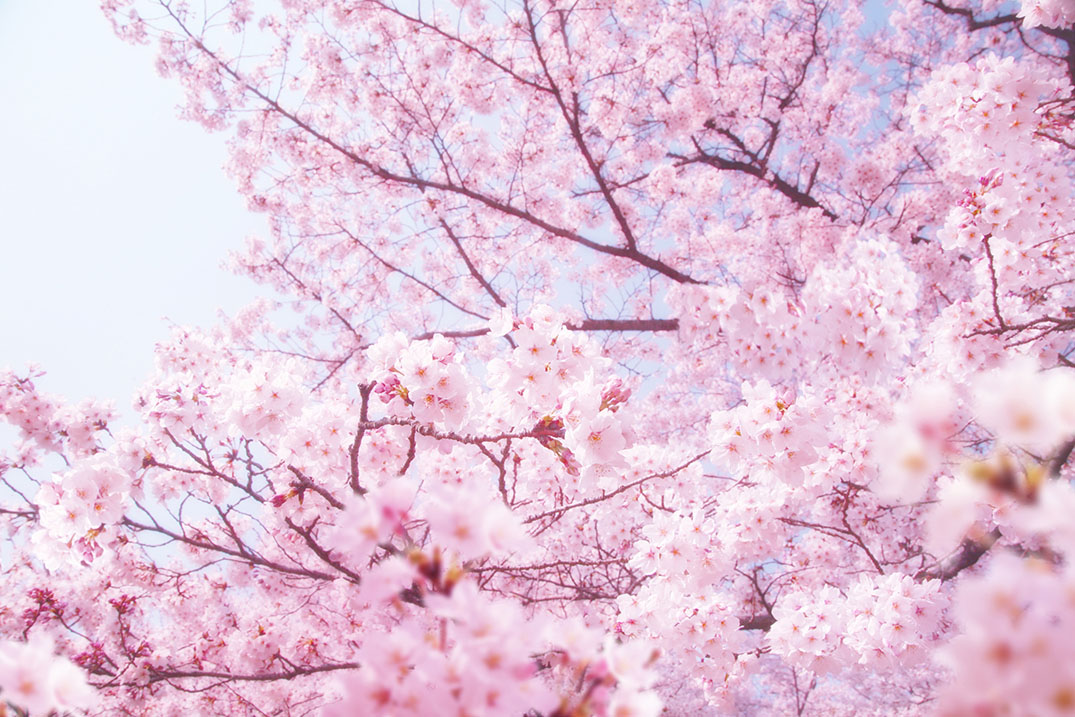
桜の木の下で「桜」の本を持ち寄ってお花見読書会がしたいですね。桜の木の下には死体が埋まっているかもしれないし、鬼が現れて花びらとなり散ってしまうかもしれません。そんな桜の季節に思うことです。
“ひとは人生で本当になにかができるのだろうか”
『心は燃える』ル・クレジオ(著)
1940年、南仏ニース生まれ。1963年のデビュー作『調書』でルノドーを受賞し、一躍時代の寵児となる。一方、インディオの文化・神話研究など、文明の周縁に対する興味を深める。2008年ノーベル文学賞を受賞する。
装丁に魅せられて購入。表紙に使われた美しい赤は、燃える心とその熱量を見事に表現しているように感じる。本書は短編集だが、表題作が本書の半分近くを占める。7作品のほとんどが若者を中心に描かれる。
『心は燃える』
堅実な姉・クレマンスは少年事件を担当している女性判事だ。夫のポールと暮らしている。彼女が、昔撮った写真を眺めるところから物語は始まる。写真に写る3歳の女の子は、妹のペルヴァンシュ。妹は今、素行の悪い仲間達と交わり、母親・エレーヌの家を出て生活をしている。堕落するペルヴァンシュには、もう何もしてやれない、遅すぎる、遠すぎる、違いすぎる。そんな想いを抱き、懐かしい写真とともに過去を振り返る。
姉妹がどうしてここまで違う運命をたどることになったのか。どうやら幼少期に余儀なくされた移住生活がトリガーとなるようだ。エレーヌの無責任さや姉に対する劣等感よりも、メキシコと西欧の文化の不均衡さによって受けた傷が、柔軟さに欠けるペルヴァンシュの人生に暗い影を落とす。
本能は心に溶けるのだな、と感じる。育った環境やDNAそのものより本能は、より心に敏感に反応する。人物たちの感情の襞は繊細で、読むものを感情の底へと落としてゆく。
本文全体から香る色彩豊かな表現は、日本文学ではお目にかかれない。その華やかさと美しさに衝撃を受けた。ノスタルジーを語る上でも、鮮明な色彩を持つ記憶は欠かせないということをクレジオから学んだ、そんな一冊。
【投稿者】KURI






